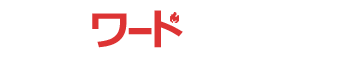Googleに排除措置命令、公正取引委員会が独禁法違反を認定
公正取引委員会(公取委)は2025年4月15日、米グーグルに対し、独占禁止法違反に基づく排除措置命令を出しました。
命令の対象となったのは、グーグルが提供する基本ソフト(OS)「Android(アンドロイド)」搭載のスマートフォンに関する取引慣行で、競合他社の排除につながる契約を端末メーカーなどと結んでいたと認定されました。
GAFAMと呼ばれる米IT巨大企業への排除措置命令は日本で初のケースです。
「Google Play」の条件に「Google検索」や「Google Chrome」を強制
公取委の発表によれば、グーグルは2020年7月以降、Android(アンドロイド)端末のメーカーに対し、自社のアプリストア「Google Play」を使用する条件として、「Google検索」アプリや「Google Chrome」ブラウザの事前インストールを義務付けていました。
さらに、これらのアプリやウィジェットをスマートフォンの初期ホーム画面の目立つ位置に配置するよう求め、検索エンジンの既定設定もグーグルに固定する契約を交わしていたといいます。
また、広告収益の一部を端末メーカーなどに還元する代わりに、ヤフーなど他社製の検索アプリをプリインストールしないよう要求する契約も締結。
こうした条件は、日本国内で販売されるアンドロイドスマートフォンの少なくとも8割を占める6社以上のメーカーとの間で締結されていました。
「拘束条件付き取引」として独禁法違反を認定
公取委はこれらの契約を、「拘束条件付き取引」として、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項)に違反すると判断。
競合他社の市場参入を妨げ、ユーザーの選択肢を狭めているとして、違反行為の中止や再発防止を命じました。
加えて、今回の命令では初めて、グーグルから独立した第三者による監視体制を導入。
今後5年間、措置の履行状況を監視し、公取委に報告することが義務付けられました。
命令に従わない場合、懲役や罰金といった刑事罰の対象となります。
グーグルは反論「競争を促進し、選択肢を提供してきた」
グーグルはこの命令に対し、「当社と日本のメーカーや通信事業者は、グーグルを最良の選択肢として自主的に選択しており、消費者の皆様にもより多くの選択肢を提供してきた」として遺憾の意を表明。
その上で「命令の内容をよく確認し、今後も日本の消費者にとって良い選択肢となれるよう努力する」とコメント。
今回の排除措置命令を精査し、今後の対応を慎重に検討するとしています。
背景にはグローバルな監視強化とAI検索の台頭
今回の日本での命令は、世界的な規制強化の流れと連動しています。
欧州連合(EU)は2018年、グーグルが検索サービスとアプリストアを抱き合わせて提供していた行為を違法と判断し、43億4000万ユーロ(約7000億円)の制裁金を科しました。
米司法省も2020年に同社を提訴し、2024年には米連邦地裁が「検索サービスの独占状態」を認定。クロームやアンドロイドの事業分割を含む是正策を求めています。
さらに、近年では生成AIの進化により、「対話型検索」の利用が急速に拡大。
グーグルが長年強みとしてきた「キーワード検索」型の優位性が揺らぎつつあり、新たな検索サービスの台頭を後押ししています。
公取委はこのタイミングでグーグルの優遇状態を是正しないまま放置すれば、新興勢力の参入機会を奪いかねないとの危機感から、今回の命令に踏み切りました。
今後は「スマホ新法」による追加規制も視野
今回の命令と合わせて注目されるのが、2025年12月までに施行予定の「スマホソフトウェア競争促進法(スマホ新法)」です。
スマホOSやアプリ配信市場での競争促進を目的に、ブラウザや検索エンジンなどの選択肢表示の義務化、他社の排除を目的とした条件付き契約の禁止、違反時の課徴金(最大売上高の20%)などを規定するものです。
現在の独占禁止法と比べて、新たな制度では違反に対する課徴金が3倍以上の水準に引き上げられています。
さらに、過去10年以内に同様の違反を繰り返した場合には、課徴金率が最大30%に増加する厳しい措置が取られます。
公取委はグーグルだけでなく、アップルやその子会社iTunesも新法の対象とし、デジタル分野での監視体制を一段と強化しています。
まとめ
今回の排除措置命令は、公正な市場競争を守るための重要な一歩です。
グーグルの影響力が強すぎることによる市場のゆがみが、検索分野やスマホアプリの選択肢に影響を与えていたことが明らかになりました。
世界的に進むIT規制の流れの中で、日本も独自に対応を強め、今後の法整備と実効性の確保が問われる段階に入っています。
今後は第三者の監視や新しい法律の施行により、スマホの世界でもより自由で公正な競争が進んでいくことが求められます。
ユーザーとしても、自分に合ったアプリや検索サービスを自由に選べる時代が近づいているといえそうです。
投稿者

- 編集部
- GoogleやYahoo、BingやYouTubeなど、あらゆる検索エンジンの情報やアルゴリズムについて、日々リサーチ&アナライズするサジェスト汚染対策のプロフェッショナル集団「風評ワード解決.com」。サジェストやSEO、風評被害対策を中心に、最新のSEM(検索エンジンマーケティング)に関する情報をご紹介します。